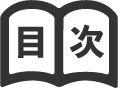ハーフ学者ふたりが語る、ニッポンのレイシズム 第1回

チャリツモの記事に医療監修者として携わってくれている精神科医・阿部大樹さんが、昨年から翻訳家としても大活躍中です。初の翻訳書「精神病理学私記」は第6回日本翻訳大賞を受賞し、今年4月には2冊目となる翻訳本「レイシズム」を出版されました。
「レイシズム」は日本人論の古典「菊と刀」で有名な文化人類学者ルース・ベネディクトの著作。人種・国家・言語・宗教・文化など「人間のまとまり」に優劣があるかのように宣伝するレイシストたちの言説を、一つ一つ論破している本書は、奇しくも「Black Lives Matter」と言われる反人種差別の運動が巻き起こる直前に出版されたこともあり、たいへん注目を浴びています。
本連載では、2019年12月、「レイシズム」を翻訳中だった阿部さんが、新進気鋭の社会学者・ケイン樹里安さんと“レイシズム(人種主義)”をテーマに行った対談の内容をお届けします。
フランス人の父を持つ阿部さんと、アメリカ人の父を持つケインさん。日本ではいわゆる“ハーフ”と呼ばれる二人。それぞれ日本社会で“ハーフ”として暮らし、そして学者の視点で社会を見てきた彼らが、日本における“レイシズム”について、ざっくばらんにお話しします。
プロフィール
-

阿部 大樹 精神科医・翻訳家 -
精神科医。医師として臨床に携わる傍ら、翻訳家としても活躍。
2019年に刊行した初の翻訳書「精神病理学私記」(日本評論社)が日本翻訳大賞を受賞。同書は現代精神医療の基礎を築いたアメリカの精神科医H・S・サリヴァンが生前に書き下ろした唯一の著作で、サリヴァン自身の性指向とアルコール耽溺を参照軸としつつ、スキゾフレニア、パラノイア、そして同性愛などを語る内容となっている。
また、翌2020年に出版した2冊目の訳書「レイシズム」(講談社学術文庫)は、日本人論の古典「菊と刀」でも知られるアメリカの文化人類学者ルース・ベネディクトの著作「RACE AND RACISM」の新訳書。1940年に発表され、「レイシズム」という言葉が広く知らるキッカケとなった本作を、多くの人に読んでもらえるよう平易な言葉で新たに訳し下ろした。
-
 ケイン
ケイン樹里安 社会学者 -
社会学者・大阪市立大学 都市文化研究センター 研究員。主たる研究テーマは「ハーフ」と「よさこい踊り」。
2019年に出版した「ふれる社会学」(北樹出版)は、メディア、家族、労働、余暇、ジェンダー、セクシュアリティ、差別、人種などの視点から、身近でエッジのきいた14のテーマを読み解くことを通して、社会の大きな仕組みにふれる入門書。飯テロやスニーカーといった題材から、日本初「ハーフ」の章がある社会学の入門書としても注目されている。刊行後、たちまち4刷。
た・い・だ・ん
スタート!
人種ってなに?レイシャライゼーションとは?
今回のテーマはずばり「レイシズム」。日本語だと人種主義だとか人種差別といわれるけれど、そもそも人種とか人種差別って何なのでしょう?
「黒人は足が速いよね」
「ハーフってイケメン or 美人だよね」
これってどういうこと?
ヘイトスピーチって聞くけど、これって表現の自由の範疇?それとも刑罰の対象?
こうしたことは、分かっているようで、実はなかなかつかめないものです。
実は「人種」というまとまりがあることは、人類学の観点からも、遺伝学の観点からも否定されています。
それでも、私たちは日々、国籍や民族を主語にして物事を語りがちです。
レイシズム、人種主義をどうとらえるか。ボク自身は人種主義という言葉よりも、「人種化(レイシャライゼーション)」という言葉をよく使います。人種に化ける。
僕たちは、人種というものがあるという前提で話しがちだし、その前提で社会が回っています。

大坂なおみフィーバーを再考しよう
まず始めに、大坂なおみさんのインタビューについて取り上げようと思います。
2018年9月にテニス選手の大坂なおみさんが、全米オープンで優勝した。そのあと日本に来た際に行われたインタビューについてです。
「大坂なおみフィーバー」って言われてましたよね。あれは何だったんでしょう。
全米オープンの少し前くらいから「日本で深夜放送していたテニスの試合で大坂なおみっていう選手がいるらしい」「結構強い選手らしい」「インタビューを見るとめちゃくちゃ英語が流暢らしい」…。そういったところから入って、メディアが次第に「どうやって片言の日本語をしゃべらせようか」という方向にシフトしていったような気がします。
はじめの頃は英語でスピーチしていたはずなんだけど、だんだん片言の日本語を面白がるような形で商品化されていった。
世間の声も「何か片言の日本語をしゃべっていてかわいい」とか「片言でも日本語を話すから日本人なんじゃないか」とかいうものがでてきて…。
「大坂なおみは日本人なのか」問題が取り上げられていたところに、全米オープンでの優勝。
その瞬間、それまでの議論はおいておいて、メディアの見出しは「日本人初優勝!」となりましたよね。それを見ていて、「唐突に日本人になるんだなあ」と思いましたね。※
「優勝おめでとうございます!日本語話していますか?」
僕が印象的だったのは、優勝会見での3つの質問ですね。
「ご両親とは日本語でやり取りしてますか」
「日本語はどうやって勉強していますか」
「あなたの活躍が古い日本人像を見直すきっかけになると思いますか」
スポーツ選手の優勝会見で、日本語の運用能力が質問されるって、ちょっと考えてみるとおかしな話ですよね。
1年以上経った今振り返るからこそ「的外れだね」ってなると思うんですけど、そういう質問が出る背景、記者さんとか、その上司にあたるデスクとか、そこで想定されている読者像とか、よく振り返っておくことが必要であると思います。功績と関係ないプライベートなことを聞くことに、どういうメカニズムが働いているのか。
私は精神科医をしていますが、いわば人のライフヒストリーを聞く仕事です。初対面の人に、「あなたはどこで生まれましたか?」「何人兄弟がいますか?」場合によっては親からの性虐待などについても聞かなくてはならないときがあります。だからこそ、ライフヒストリーに触れるときにはこれ以上ないくらいに慎重に話を進めます。
人に何かを伝えたり、報道したりする時は、ストーリーを作ることは避けられません。人の記憶に残すにはストーリーが必要です。それが如実に表れているのが世界中の宗教なのですが、どんな聖典でも必ずストーリーに加えて教訓、という形になっていますよね。記憶に残すためにストーリー化しています。
ただ、ストーリー化する際に、特に今を生きている著名人をストーリー化する際には、気を付けないといけないことがあります。
私たちが本で読むような過去の偉人のストーリーは、時間をかけてゆっくりと形成されたものですが、今を生きる人の場合、基本的にライフヒストリーは自分から話すものであって、人から聞かれるものではないということです。
「お家では何語をしゃべっていますか」とか「どこで生まれましたか」とかは、なんとなく初対面の人に聞いてもいいだろうと考えている人もいますけれども、たとえば初対面の人にいきなり学歴とか年齢について聞かないように、やはり一対一の関係性ができていないときに聞くようなことではありません。
でもエスニシティに関わる質問に、そのデリカシーの感覚があまり働かない。「よそもの」というかなり強いメッセージを伝えうることでもあるのに。その部分への意識は、これから持っていく必要があると思う。

始まってしまった「日本人とは何者か」ゲーム
大坂なおみさんの記者会見は、これまでもあった人種化についての問題がわかりやすい形で表面化してしまったんだと思いますよ。
どういうことかというと、「日本人」と言ったとき、その中身は実はめちゃくちゃ複雑だということが明らかになってしまった。
日本人といっても、どこで生まれ育ったか、ジェンダーや学歴、家族構成など、本当はみんなバラバラなんだけど、なんとなく「とりあえず日本人ってこんな感じ」っていうふんわりとしたイメージがあると思うんです。今回のインタビューで、その「日本人のイメージ」が揺さぶられてしまったのだと思います。たぶん。
「日本人のイメージ」から外れるような、外国にルーツを持つ人は、実はすでにたくさんいて、朝日新聞の報道によると、新生児の50人に1人がいわゆる“ハーフ”だといいます。でも、なぜか多くの人は、普段はそうした多様性を見ないようにしている。
今回の「大坂なおみフィーバー」が出たとき、この「日本人って誰なんだ?」という根本的な問いが「大坂なおみは誰なんだ?」 という形で表面化したんじゃないでしょうか。
SNSを見ていると、「大坂なおみは日本人らしい」 「いや、 日本人らしくない」「肌の色が違うよね」などと、ご本人のアイデンティティという極めてプライベートなことがらについて、人々がいろいろ好き勝手なジャッジを披露し合っている状況でした。
大坂なおみフィーバーについて、僕が今思うのは「日本人とは何者か、再定義しないといけなくなっちゃった現象」という側面があったんだな、ということです。大坂なおみさんを介して「日本人とは何者か」ゲームが始まっちゃった感じです。
片言の日本語が「日本人らしくない」とか、そうした話をすることで、つまり、「大坂なおみとは何者か」という話をすることで、実際には複雑であるにもかかわらず一枚岩的に想像してきた、そんな「日本人らしさ」を再確認する側面があったのだと思います。
面白い比較だと、ちょうど直前にカズオ・イシグロさん※がノーベル賞を取ったことがニュースになっていましたよね。カズオ・イシグロに対しても「彼は日本人か」という議論があったところに、大坂なおみさんの優勝のニュースがありました。
カズオ・イシグロは、アイデンティティについて「明確な答えはない」「英国の作家や日本の作家であることがどういう意味かもわからない」「いつもただのひとりの個人として書こうとつとめてきた」という風に、わかりやすく答えないという姿勢を貫いています。
大坂なおみさんが抹茶アイスが好きっていう話がありましたけど、もしもカズオ・イシグロさんもそういう話をするひとだったら、同じようにメディアに消費されていたかもしれませんよね。

自己紹介が上手な“ハーフ”の子どもたちと、そうではなかった大坂なおみ
日本人とは何か、という枠ね。「日本人の枠」の話って、“ハーフ”の子どもたちは、間違いなく全員体験していることだと思う。
「○○語しゃべれる?日本語は何歳で覚えた?夢は何語でみる?親とは何語でしゃべるの?」とか、まだ自己紹介すらしてない相手からたたみかけるように聞かれちゃうこともよくある。悪意があるとはもちろん思ってないんだけど。
大坂なおみさんの記者会見では、それがほとんどそのまま提示されましたね。
自分たちが属しているコミュニティの住人=“日本人”なのかを無意識にチェックしているんだと思います。値踏みをしているというか。
大坂なおみさんの場合もどこまで日本に染まっているのかをチェックするツールとして言語が使われたと思うんです。
日本にいる”ハーフ”の子たちは、「おうちでは何語しゃべっているの?「納豆食べれるの?」「日本語書けるの?」という日本人性の確認を、幼稚園くらいからずっと経験しています。僕自身もそうですが、見た目で“ハーフ”だとわかる人は幼少期からずーっと聞かれてきた質問です。
そうすると、次第に答えるのに慣れてくるんです。全員がそうだとは限りませんが、しばしば自己紹介が上手な小学生が生まれます。子どもながらに「だいたいこんなこと、こんなテンションで聞いてくるんだろうな」「私の鼻の高さや髪の毛の色に注目しているな」と、だいたい相手の聞きたいことがわかってくる。
でも、大坂なおみさんにはそれがなかったんですよね。
日本に住んでいる人、それも記者さんであれば、“ハーフ”の人に対して「英語しゃべれるの?」というような質問をしたことがない人っていないと思うんです。そして質問した相手は、自分のルーツについて上手いこと起承転結にしゃべってくれた経験がある。
ところが、そんな常識が大坂なおみさんには通用しなかった。
日本人性の確認に慣れていなかった大坂なおみさんは、取材者の意図がわからず、自ら語ることができなかった。いや、できなかったのではなく、そうした質問を受け、とっさに切り返す必要性が生じない状況で暮らしてきたのだと思います。だから、困惑したのだと思います。
そして記者の側も困惑して、たたみかけるように日本人性を確認するための質問を繰り返してしまった。
確かにそうかもね。
相手が何者なのか。同時に自分が何者かも、本当はあまりクリアではないにも関わらず、よくわからないと不安になる。
アイデンティティ(自分が何者か)って不思議ですよね。だって、今日の自分と明日の自分は違うじゃないですか。哲学的な話じゃなくって、単純に違う。食べるものも飲むものも、感じていることも違う。自分についてよどみなく話すとか、一貫性のあるストーリーを描くって、実はあまり普通なことではないんです。
「そもそも自分は何者か」という問いであるわけですから。
なかなか興味深いね。
まず、なんでこの話をはじめにしたかというと、「著名人のライフヒストリーと一般の生活者のライフヒストリーはどう違うのか」、そして「ライフヒストリーは語られるものか、聞き出すものか」「聞き出すときはどういう順番で聞くか」ということを聞いてみたかったんです。
日常生活で自分が誰かに出会った時、どういう風にしているのか。それが著名人のインタビューになった時にどう変わるのか、ということを考えてみることに意味があるのではないでしょうか。

次回の記事に
つづく!
チャーリーのひとこと
日本人とは何か。それは、答えのない問いなのでしょう。
人間は、それぞれ個性を持った存在です。しかし、時にその人の人間性よりも、国籍や外見が重要視されてしまう場面があるようです。国籍や外見に基づく分類は、一見便利ですが、知らずに人を小さな枠組みの中に押し込め、時に人を傷つけます。
純粋なゆえに時に残酷な子どもたちが、相手の身体的特徴や、聞きなれない名前について質問するのと同じように、メディアや大の大人が堂々とプライベートな話題に土足で踏み込んでいく様子に対して、違和感を持つことは大切かもしれません。