
自分の好きなことを仕事にしたい。憧れの仕事で成功したい。という夢を持つ女性にとって、ロールモデルとなる女性の存在は大きい。
しかし彼女たちのインタビューの内容はその“経歴”に着目されがちで、私たちはその成功の裏にある“ストーリー”を知らない。
彼女たちのストーリーを知ることができれば、私たちはそこから何かを得たり、励まされたりするはず。
この連載では、様々な分野で活躍中の自分らしく輝く女性たちのストーリーを紹介していきます。
ライター紹介
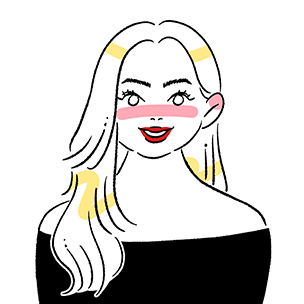
国際人権NGO勤務。博物館学芸員資格保持のファッションオタク。
“Empowered Women Empower Women.”

「いつも自分がいるところで精一杯やるというのが私の信条です」

HER STORY vol.10
青木美由紀
NPO法人 EUREKA 副代表/大学学生アドバイザー
子どもの頃の夢は?
小学校の先生。
田舎だったので選択肢が少なかったのもありますが、安定していてかつ人から敬われる職業であることに惹かれていたと思います。
自分がやりたいことに気づいたのはいつ、どこで?
16歳の時、語学留学でアメリカのカルフォルニア州に行きました。当時から人と話すのがとても好きだったので、英語を話せれば世界中の人々とコミュニケーションを取れるのではと思ったからです。人種のるつぼであるアメリカでは、英語だけでなく他の言語にも多く触れる毎日でした。中でも私が住んでいた地域はメキシコ人が多く、次第に次はスペイン語を学びたいと思うようになりました。そんな高校時代の体験から、大学では英文科に進学。第二言語でスペイン語を学び、大学3年の時にはスペイン語を勉強しにメキシコでホームステイをしました。
その留学先のメキシコで、7歳の少年が路上でチューイングガムを売っていた姿を見たんです。当時の私は何も知らなかったので、無情にもその少年に「なんで学校に行かないの?」と聞いてしまったんです。そうすると、彼は「行かないんじゃなくて行けないんだよ」と言いいました。あの時の衝撃は忘れられません。
当時私は日本ではアルバイトとして家庭教師をやっていて、その少年と同い年の少女を教えていました。彼女は家庭教師だけでなく、ピアノや公文など多くの習い事をしていました。その一方で、海を渡ったメキシコでは義務教育さえ受けられない子どもがいる。この格差の現実に打ちのめされたのを覚えています。テレビでUNICEFの親善大使だった黒柳徹子さんやアグネス・チャンさんが出演されている番組を見て、貧困問題については知ってはいたけど、実際に目の当たりにすると、この不平等への悲しみが怒りに変わりました。
この経験がきっかけで、子どもたちの教育格差を是正したい!と思い国際協力の道を志しました。
ファーストキャリアはどう選んだ?
大学時代の専攻が英文学だったので、もっと教育のこと学びたいと思い、大学卒業後はアメリカの大学院に進学し、教育学の修士号を取得しました。卒業後はNGOで働きたいと考え、実際に日本のNGOで最終面接まで進んだのですが、そこで面接をしてくださった方に「あなたは1回社会に出て、3年間は働いてみなさい。その後にまだうちに来たいと思っているなら歓迎するから。」と言われ、その時は不採用になったのです。
私自身、大学院で専門的に教育学を学んだものの、職務経験の無い自分にとって、その知識は机上の空論になりかねないという自覚はありました。また、私は高校留学で1年留年して、大学でもメキシコ留学で留年、そこから大学院にも進学したので、卒業した時点で26歳でした。同世代はもう3〜4年間の社会人経験を積んでいるわけですから、職務経験がないことに対して、当然焦りがありました。そんな心境もあり、面接官の言葉が妙に府に落ちた私は、一度民間企業に就職して社会経験を積むことにしたんです。
そうしてファーストキャリアでは、語学力を生かして働けるマーケティングリサーチの仕事につきました。遅れている時間を取り戻すように、1年で3年分働ける会社を選んで、毎日必死で働きました。これは自分でも予想外だったのですが、マーケティングリサーチの仕事は自分に合っていて、楽しくてしょうがなかったんです。その後、外資系広告代理店にヘッドハンティングされ転職ましたが、そこでも毎日の仕事が楽しかったです。
キャリアの最大の転換点は?
毎日マーケティングリサーチの仕事に熱中していたので、国際協力の道から外れてしまっているという焦りは特にありませんでしたが、企業で利益ばかりを追求しているので、 自分らしさは失われていってしまうと感じていました。なので、通訳ボランティアなどの形で、少しですが国際協力には関わるようにしていました。民間企業での仕事も楽しかったのですが、どこかでは国際協力に関わっていたいという気持ちはずっとあったんだと思います。
そんな中、29歳の時に結婚をしました。夫が大学時代、ケニアに留学していたことがあったので、アフリカに新婚旅行に行くことになったのですが、これが私のキャリアの転機になりました。
アフリカの地で時間を過ごしていると、頭の片隅にあった国際協力への想いがふつふつと湧いてきて、導かれるように転職活動をして、草の根NGOに就職しようと決意しました。
大学院では都会に住むストリートチルドレンの研究をしていて、エイズやドラック依存 に苦しむ子どもたちと関わっていたこともあり、国際協力の中でも「教育と健康」が私のキーワードでした。教育と健康分野で活動しているNGOに就職し、最初は東ティモールの事業のプロジェクトオフィサーとして着任しました。その後、HIV/エイズの事業で南アフリカに駐在することが決まりました。国際協力の道を志した時から、「いつかアフリカで仕事をしたい」と思っていたので、とても嬉しかったのを覚えています。
NGOに就職すると、給料は民間にいた時の半分以下になりましたし、待遇も企業時代と比べたら良くありませんでしたが、5年半マーケティングリサーチの仕事をやってきたので、自分の仕事に自信もありましたし、クライアントもいたので、最悪元のマーケティングの仕事に戻ればいいやと考えていたので、思い切って飛び込むことができましたね。定年を迎えるときに、やっておけばよかったと後悔する人生は歩みたくなかったので。

キャリアの中で得た最大の教訓は?
やりたいことは口に出すこと!
私の場合は、「40歳までに本を書きたい」と「大学で教鞭を取りたい」でしたが、どちらも叶いました。自分がNGO職員として経験してきたことを次世代に伝えたいと考えていて、その手段が本と教鞭を取ることだったんです。
「南アフリカでの経験を次世代に伝えるために、本を書きたい」と周りに話していたら、一緒に活動していた人の繋がりで出版が実現しました。『ぼくは8歳、エイズで死んでいくぼくの話を聞いて。―南アフリカの570万人のHIV感染者と140万のエイズ孤児たち』(合同出版)という本です。また、NGO関係の知り合いの教授とのご縁で非常勤講師として、自分の経験を活かした授業も持たせて頂くことができました。人と人との繋がりは本当に大事で、最初は不可能に思える目標でも、言い続けたらそこに繋がる道を他の人が作ってくれたりするんですよね。
また、「人生遠回りも大事」とも痛感しますね。
大学で教鞭を取っていた時に、「地球社会と企業」というSDGsやCSRについての授業を持っていたのですが、これはNGOでの実務経験だけでなく、企業で働いた経験があってこそ出来たことだと思います。民間企業で働いている時は、国際協力とは直接関係のない業務内容でしたが、それでもベストを尽くしていれば、このために自分がやってきたことがあるんだなと思える瞬間が来るんですよね。
現在私は清泉女子大学でSEO (Student Experience Officer)という新しく作られた役職を担当しています。学生が実際の社会とつながり、現実的な体験を通じた学びと活動を行うことができるようにサポートをする専門スタッフなのですが、私にとっては、これまでの様々な経験をふんだんに活かすことができる仕事で、しかも次世代を担う女性たちから元気をもらうことができ、とても楽しいです。

駆け出しの頃役に立ったアドバイスは?
やはり新卒で受けたNGOでの面接で言われた「1回社会に出てきなさい」という言葉は、素直に聞いて良かったなと思いますね。
ちなみに、そう言ってくださった方とはその後再会することができました。私のことを覚えていて下さったので、親身になってしてくださったアドバイスだったのだと思います。
また、大学時代の教授にも感謝しています。26歳で社会人経験なしで日本に帰ってきて、自分に仕事はあるのかなと不安になっていた私に、「これからは男性も女性も関係なく働く時代だから、心配しなくていい」と鼓舞してくれました。当時からしたらこの考え方は珍しいことで、すごく勇気づけられましたね。
今の自分から見て、駆け出しのときこうすればよかったと思うことは?
ある程度、今までの自分を正当化して生きていると思います。(笑)
それでも、最後の力が出しきれなかったな、と幾つかの事を後悔していますね。
例えば、大学院留学中にインドの孤児院にインターンに行きたかったのですが、お金がなくてできなかったんです。でも、どうにかしてインターンしておけば良かったな、行っていたらどうなってたかな、と思ってしまいますね。
また、同じく大学院時代に教授に論文を学会に提出する事を勧められたのに、やりきれず出さずに終わってしまったのも後悔していますね。これも、出していたらどうなっていたかな、とふと思い出すことがあります。
キャリアや仕事のために払った最大の犠牲は?
出産してからは海外出張を無しにしました。子どもとの時間をちゃんと取る、と自分で決めたからです。もちろん現場に行きたいのに行けないというジレンマはありましたが、キャリアのために子どもとの時間を犠牲にはしたくなかったんです。
キャリアの中で経験した最大の誇りは?
一番嬉しかったこととして忘れられないのは、南アフリカに駐在している時のことです。
当時在籍していたNGOのプロジェクトで、HIV陽性者やエイズ患者たちが栄養のある野菜を食べられるよう、地域に家庭菜園を導入するために、パーマカルチャーのトレーニングを提供していました。
そのトレーニングを受けていた地元の14歳の少年がいたのですが、私が彼に初めて会った時に「将来何になりたいの?」と聞くと、何も答えなかったんです。何にも夢がなかったのか、英語が通じてなかったのか…その後継続して行っていたトレーニングを通して、少しずつ彼と親睦を深めていくと、次第にどんどん心を開いてくれて、私が普段乗っている車が彼の家から見えると、嬉しそうに走ってきてくれたりするようになりました。そんな彼にトレーニング修了後に、将来の夢を再度聞いてみたんです。そうすると、私たちがトレーナーとして雇い、彼に農業を教えていたトレーナーがいたのですが、「自分もトレーナーになって、今度は自分が人々に農業を教えたい。」と答えたんです。
栄養のある野菜を食べてもらう事がプロジェクトの目標だったのですが、それ以上に彼が夢を語れるようになった事がすごく嬉しかったです。NGOで草の根の活動をしていると、規模は小さくとも、プロジェクトの目的以上の影響を人に与えることができると実感しました。
P.ドラッカーの言葉に『非営利機関は、人間を変革する機関である。したがって、その成果は、つねに人間の変化のなかにある。』というものがあるのですが、本当にその通りだと思いますね。ちなみに、夢を語ってくれた彼とは今でも家族のような関係です。彼の娘に名前をつけさせてもらったり、私のことを”ママ”って呼んでくれています。

長い1日の仕事を終えてから楽しみにしていることは?
私は現在、夫の駐在に帯同する形で家族と一緒に南アフリカのヨハネスブルグで生活しています。以前仕事で駐在していた国にまた戻ってこられて嬉しいです。リモートワークをしているのですが、仕事の拠点は日本にあるので、時差の関係でちょうど子どもが学校行っている時間に私は仕事ができます。
私は趣味が多くて、生花や書道、編み物、お菓子作りなどを空いた時間で楽しんでいます。コロナ禍で以前よりも自由に使える時間が出来たので、趣味が増えましたね。仕事の時は左脳を使って、趣味の時は右脳を使っている感覚です。趣味に一気に集中するのは良い気分転換になりますし、マインドフルネスに繋がる大切な時間だと思います。
1日の良いスタートを切るために、朝いちばんにすることは?
家族の誰よりも早く起きて自分ひとりの時間を楽しみます。呼吸法を学んでいるので、呼吸を整えて、ストレッチをして、朝日を眺めると、今日も新しい一日が始まるなと前向きな気持ちになります。その後は子どもたちのお弁当を作って、学校に送り届けます。(ヨハネスブルグは治安が悪いので、子どもたちは車で送迎しないといけないのです)
夜通し考えてしまうような不安や悩みは?
2020年は、コロナ禍でとにかく不安な毎日でした。今までずっとキャリアを積み重ねてきましたが、パンデミック当初は仕事をしていなかったので、私のステータスは”駐在妻”だったんです。ただでさえ仕事をしていない期間が3年間あるのに、コロナの影響でずっと続けてきたボランティアの活動も無くなってしまい、猛烈に不安になりました。もし夫の駐在期間が伸びて、さらにキャリアのブランクができてしまったらどうしようと毎晩考えていました。でも、不安がっていてもしょうがないので、この状況の中でも自分が出来ることを必死に考えました。私はやはり子ども支援にはずっと関わっていきたくて、また自分が最終的に帰るところは日本だと思っているので、将来的には日本の子どもたちをサポートしたいと考えました。
小学生が一番つまずきやすい科目は算数と聞いているので、楽しく算数を教えてあげられるようになりたいと思いました。現在、自分の子どもたちがシュタイナー学校に通っていることもあり、私自身がシュタイナー教育で教えている算数の美しさに魅了され、シュタイナー教育の算数教員養成講座を半年間受講して修了しました。現在オンラインで日本の子どもたちに教えています。
また、仲間5人と一緒に日本で活動するNPOを作りました。今の学校教育に不足していることー子どもたちにロールモデルを見せてあげたいという気持ちから、キャリア教育を提供しています。
不安な時って思考がネガティブになっているので、考えれば考えるほどマイナスが大きくなっていくに感じてしまいますが、そこから一歩進んでまずは行動してみるのが大事だと思います。そうすると、あの不安や悩みって大したことじゃなかったなと思えるタイミングが来るんですよね。また、今の不安な気持ちや数年後の自分の理想の姿を、まず紙に書き出してみる。書き出すことで見えてくるものがあると思うので、私もよくやっています。
憧れの、あるいは尊敬する女性は誰?
一緒にNPOの活動をしている仲間たちです。自分の家庭を超えて、地域や地域の子どもたちのために時間を惜しまずに動いている姿を心から尊敬しています。毎日精一杯やりながらも、あくまで自分も楽しくやっているところがすごいと思います。自分が楽しみながら、人のために動くことは簡単に出来ることではないです。
1日があと3時間増えたら何をする?
子どもたちとの時間を増やしたいです。9歳と11歳の男の子ですが、アフリカでの生活が長いからか、とても伸び伸びと成長していると思います。今は一緒に編み物をしたり、お菓子作りをしたり、絵を描いたり。こんな何気ない親子の時間を大切にしたいと思います。

世の中にもっとあって欲しいものは?減って欲しいものは?
“Ubuntu”という南アフリカの言葉があります。「あなたがいるから私がいる」という意味の言葉で、他者を思いやる気持ちを表した、南アフリカではみんなの合言葉のようになっている言葉です。共生をよく表した言葉で、この言葉のように、「みんながいるからこその自分なんだ」という意識がもっと広がってほしいと願っています。
無くなってほしいのは格差です。私が大学生の時にメキシコで目にした教育格差も、30代で南アフリカで目にした経済格差や命の格差も、現在も是正されないどころか、どんどん広がってきています。
今後の展望は?
今までも今後も、「いつも自分がいるところで精一杯やる」というのが私の信条です。
現在は駐在妻という立場で、治安上、あまり自由に行動できませんが、現地の友人たちの協力も得て、これまでタウンシップで暮らす子どもたちにいろいろな体験の機会を提供してきてきました。体験はその人の人生を作ります。また、実際に経験しないと様々な選択肢があることに気づくことが難しく、貧困のスパイラルから抜け出せなくている子どもたちもたくさんいます。今ここ南アフリカでも、日本に帰ってからも、多くの子どもたちが、自分たちで未来を開いていけるよう、出来るだけ沢山の経験をプレゼントしてあげたいです。














