
自分の好きなことを仕事にしたい。憧れの仕事で成功したい。という夢を持つ女性にとって、ロールモデルとなる女性の存在は大きい。
しかし彼女たちのインタビューの内容はその“経歴”に着目されがちで、私たちはその成功の裏にある“ストーリー”を知らない。
彼女たちのストーリーを知ることができれば、私たちはそこから何かを得たり、励まされたりするはず。
この連載では、様々な分野で活躍中の自分らしく輝く女性たちのストーリーを紹介していきます。
ライター紹介
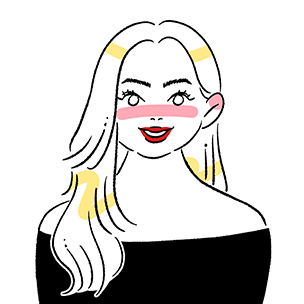
国際人権NGO勤務。博物館学芸員資格保持のファッションオタク。
“Empowered Women Empower Women.”

アイデアは常に湧いてきます。やりたいことは本当に沢山あるんです/本橋弥生のHER STORY

HER STORY vol.11
本橋 弥生
美術館学芸員
子どもの頃の夢は?
いろんな世界を見て歩くこと。子どもの頃は本を読むのが何よりも好きで、色々なジャンルの本を読んでいたのですが、その中でも一番心がときめいたのは、世界の旅行記や文化、芸術に関する本でした。旅行でも、留学でも、どんな形でも、世界中の国を巡るのが夢だったんです。
キャリアに影響を与えた学生時代の経験は?
高校時代をイギリス・ロンドンで過ごしたことです。
中学校までは日本の学校に通っていましたが、親の駐在をきっかけに、子どもの頃から念願だった留学をすることができました。言語の壁があり、苦手な科目もあったのですが、芸術と体育だけは得意で自信がありました。特に芸術の授業は日本とは全く違うシステムで、日本は先生がテーマを決めて、生徒はその通りに作っていくけれど、イギリスでは生徒が一からポートフォリオを作っていきます。さらに、とにかく褒める教育だったので、自分が作った作品をよく褒めてもらえて、それが嬉しかったので、芸術の授業がとても好きでした。
正直、日本にいた頃はたまに自分で絵を描くことはあったけれど、美術の授業はあまり好きではなく、教科としてのあり方を疑問に思うこともあったほどでした。
でも、小さい頃からファッションや芸術には興味を持っていて、特に服作りや空間の演出などには関心があったので、元々好きだったものや自分の中の情熱を、イギリスで引き出してもらったのかもしれません。
今の仕事を知ったのはいつ?なぜ惹かれた?
私が高校生の頃、ロンドンでは日曜日にお店がやっていなかったので、日曜日はほとんど美術館に行っていました。無料だし、素敵な展示が多くあるので、通い詰めている内に、キュレーション(展示企画)の面白さを知るようになりました。
最初は作品自体を鑑賞することを楽しんでいたのですが、次第に、展覧会の構成や作品の並びの方に興味が湧いてきたんです。
学芸員という職業の存在を知ったのは、ロイヤル・アカデミーで開催されていたポップアートの展覧会でのことです。すごく面白い展示だったので、何度も何度も見に行ったのですが、展示冒頭の挨拶のところに担当した学芸員の名前があって、その存在を知りました。ロンドンでは多種多様な展覧会が開催されていて、当時見たオットー・ディックスやマグリットの展覧会も強く印象に残っています。学芸員の仕事は面白そうだとは思いましたが、私の場合、当時すぐに学芸員を目指そうと思ったわけではなかったです。
ファーストキャリアはどう選んだ?
大学では日本に戻り、フランス文学を専攻しました。イギリスでの高校生活は、英語の語学力が足りないことを理由に諦めなければいけないこともあったのですが、日本語ならば何でも好きなことを学べると思うと嬉しかったです。昔から言語が好きだったので、他の言語をやりたいなと思い、また当時フランスの映画が流行った時期だったので、フランス文学を選びました。
文学を学んでいたのですが、次第に自分はやはりアートに関わることがしたいと思い、大学院では美術史の研究をすることにしました。美術史の中でも、「まだあまり知られていないことを自分が掘り下げて研究して、世の中の人に知ってもらいたい」という思いがあったので、当時日本ではまだ研究が進んでいなかったハンガリーの美術史を選びました。また、ハンガリーの首都ブダペストは、ヨーロッパの中でも「東欧のパリ」と呼ばれていて、人々の憧れが詰まった場所だったので、私も実際に行って見てみたいと思っていたのも、ハンガリーを選んだ理由の一つです。「ヨーロッパの中のアジア」と呼ばれていたのにも好奇心が掻き立てられました。
日本の大学を卒業後、そのまま大学院に進学し、最初の1年はハンガリーの美術史を研究しながら、ハンガリー語学科がある大阪の大学の夏季講習にも通って、語学の勉強もしていました。大学院2年目からは、ハンガリー政府の奨学金を利用して、ハンガリーの大学院へ留学しました。博士課程では、同じくヨーロッパの中でもアジア系の言語を話すフィンランドへ留学しました。


当時は研究が楽しくて、自分がこの先どうやって生計を立てていくのかという部分を考えられていなかったのですが、指導教授や周りの人たちに職業に結びつけて考えるように言われてようやく考えだしたところ、学芸員の仕事が浮かんだので、日本の美術館での採用試験を受けて、国立新美術館で学芸員としてのキャリアを始めました。
自分がやりたいことに気づいたのはいつ?
昔からやりたいことが変わっていない気もするし、反対にいまだに自分でも気付いていない気もするんですよね。
私の場合、まだ知られていない良いものを見つけて、それを周りに伝えることが昔から好きだったように思います。小学生の頃、本を読むのが好きでとにかく沢山読んでいたら、よっぽど楽しそうに読んでいたのか、クラスメイトも本を読むようになって、先生に感謝されたことがあったんです。当時から、自分が読んで好きだった本を、友だちに勧めるのが好きでした。
今の仕事の話で言うと、人間が創り出す、すごく突き抜けたものに遭遇するのが好きです。それは絵画、ファッション、建築など、ジャンルは問いません。そういった類稀な創造力や作品をきちんと評価して、他の人に伝えたい。そうすることで後世に残していきたいと思っています。
マーケットが無いからあまり知られていない、素晴らしい作品は世の中に沢山ありますし、商業的な価値だけが、作品の価値に直結するかというと、そうでは無いと思っています。
作品をきちんと評価して、伝えていくことが出来るように、自分のフィルターを磨き続けて、素晴らしい才能を探していきたいです。
自分の仕事の好きなところは?
第一線で活躍されている方に出会えて、一緒に仕事をできることです。
中でも、私が担当させて頂いた、2016年『MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事』や2017年『安藤忠雄展―挑戦―』で、共に世界で活躍されている、ファッションデザイナーの三宅一生さん、建築家の安藤忠雄さんとご一緒させていただきました。お二人の創作に対する熱意や姿勢を間近で見させていただき、大変影響を受けました。
MIYAKE ISSEY展の準備には、構想を含めると約10年ほどかかっています。
アーカイブを整理して頂くところから始まり、2、3年経った時点から徐々に打ち合わせを始めて、段々と回数を増やしていって、具体的な部分を長い時間をかけて決めていきました。三宅一生さんご本人の、展覧会開催直前の最後の一瞬までプランを練り直す、絶対に妥協しない姿に感銘を受けました。
安藤忠雄展の際には、ご本人が展示室内でフリートークを行うギャラリートークを約30回開催しました。これだけの回数を行うことは、当館としては異例のことでしたが、安藤さんは原稿なしで毎回違うことをお話しされていて、来場者を魅了していました。企画する力、実行する力、また人とコミュニケーションをとる姿勢に本当に感動しました。また、ご多忙の中でも、打ち合わせの合間にサインをされたり、休む間も無くお仕事をされていたので、その情熱に胸を打たれました。

撮影:上野則宏
キャリアの最大の転換点は?
2007年に担当した展覧会、『スキン+ボーンズ-1980年代以降の建築とファッション』でしょうか。
国立新美術館では、絵画や彫刻といった従来の美術作品だけでなく、私達に身近なテーマである建築とファッションの展示も行う、というのが開館当初からの方針でした。私個人としても、特に建築とファッションの展示を担当したいという思いがこの仕事を始めたときからあったので、当時から上司にその旨を伝えていました。
そのおかげで、学芸課の中で主にデザインやファッションといった文化史的な展示を担当させてもらえるようになっていきました。スキン+ボーンズ展は、ロサンゼルス現代美術館で開催された展覧会で、東京展での作品選定を行い、展示計画を立て、日本版のカタログを制作しました。
そのとき、作品を日本向けにアレンジして変えても良いと言われたんです。そこで、日本のデザイナーさんにコンタクトを取ったのですが、その中には三宅一生さんもいらっしゃり、その時からのご縁で、2016年『MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事』の開催に至りました。またその流れで2021年『ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会』でもご協力賜りました。振り返ると、スキン・ボーンズ展が、キャリアの原点であったように感じます。

撮影:上野則宏
仕事で最もやりがいを感じることは?
直近で担当したファッションインジャパン展に関して言うと、断片的にしか語られてこなかった日本のファッションの歴史を一本の糸でつないで皆さんにお見せできたこと。展覧会の意義に共感して下さったデザイナーの皆様や、関係者の方々のご協力のおかげで実現した、数百人で作り上げた展覧会だと思っています。
また、来館者の感想で拝見して嬉しかったのは、ファッションは文化であると認識して頂けたことや、子、親、祖父母とそれぞれの年代で異なるそれぞれの思い出を感じながらご高覧いただけたという感想を頂いたことです。
それでも、夢が全部実現したわけではなく、まだまだやりたいことは沢山あります。
展覧会を企画する時、前と同じことは絶対にやりたくないんです。前の展覧会では出来なかったことをやりたい、今までやったことのない、新しいことをやりたい、と思っています。多くの人々のご協力を得ながら膨大なエネルギーを注いで展覧会を創り上げていくので、常に今まで以上の展覧会になるよう新しい挑戦していないと自分自身、納得できないです。
キャリアや仕事のために払った最大の犠牲は?
難しいですね。正直に言ってしまうと、全部犠牲といえば犠牲かもしれません。それくらい自分の時間がないです。寝てる時間以外は全部仕事しています。でもそれは犠牲ではなく、自己研鑽であり、私の人生そのものであり、展覧会をご覧いただくかたに喜んでいただくために自主的に行っていることであるとも言えます。
職員それぞれの専門性に合わせた分業が基本の欧米の美術館とは違い、日本では、展覧会の企画、調査・研究、実際に形にするまで、その全てをごく少数の学芸員が行わなければいけないため、常に仕事に追われている状態です。
それでも、良いものを世の中の人たちに伝えたい、後世に残したいという思いが強いので、それがモチベーションとなって今まで続けてこれたのだと思います。
同じ職種の女性の尊敬するところは?
私がこの仕事を始めたばかりの頃は男性が多かったですが、今は女性の方が圧倒的に多いくらいになりましたよね。
学芸員は常に膨大な業務量をこなす必要があり、時間はいくらあっても足りないのですが、その中で自分がどういう生き方をするか、折り合いをつけて、真摯に仕事に向き合う姿勢を尊敬しています。
展覧会の全体的な方向性をディレクションするだけでなく、具体的な構成やデザインなど、細かいことまでやらないといけないので、展覧会を作るのは本当に大変なのですが、それを途中で投げ出さず、諦めず、折り合いをつけて最後までやり切る姿はとてもカッコいいと思っています。
新しいアイディアが必要な時や、モチベーションを上げたい時の特効薬は?
アイデアは常に湧いてきます。やりたいことは本当に沢山あるんです。
美術館で働き始めた頃、当時の上司に、自分の中にアイデアの引き出しは常に3つは持っているように言われました。短期的・中期的・長期的の3つに分けて、目標ややりたいことをいつも持っているように、ということです。これは20年間ずっと続けていますね。
元々やりたいことは多いので、どうしたら実現できるのかを常日頃から考えていますし、長年続けていると、その方法も分かるようになってきます。
自分が動くと、自然にアイデアが浮かびます。展覧会を企画していて、没案になったものも沢山ありますが、それらをまた別の形で企画にしたり、他のアイデアと繋げて新しい企画にしたり‥‥。やりたいことは常に尽きないですね。

今後の展望は?
社会とアートを密接に繋ぐこと。そして、後世に残していくことをしていきたいです。
長い1日の仕事を終え、オフィスを出てから楽しみにしていることは?
自転車に乗って帰ることです。地下鉄で通勤していると、地上で何が起こっているのかに気付けないんですよね。季節とか空気感とか、こんなお店が出来たんだ、とか。街や社会の変化に気付けるので、自転車に乗っている時間が好きです。
1日の良いスタートを切るために、朝いちばんにすることは?
時間があまり無いので3分くらいですが、ヨガやストレッチをしています。その日のスケジュールや仕事のことを考えたり、あとは純粋に心を落ち着けて、良い一日を過ごせるように呪文のようなものを唱えてみたりします。
1日があと3時間増えたら何をする?
自分のための時間を過ごしたいです。ゆっくりヨガをしたり、今後の目標を考えたり、友達と会ったり、美味しいものを食べたり。自由な時間は新しい発想をするためにとても大事なことだと思います。
世の中にもっとあって欲しいものは?
新しいものを発想する創造力。自由な時間や遊び、自然を見たり、旅行をして色々な景色を見たりする。そういうことでクリエイティビティが育つと思っています。
私自身、高校時代に自由でクリエイティブな型破りな先生方に教わったことで、自分の人生が変わったと思うので、色んな人に会って、様々な経験をすることが大切だと感じます。















