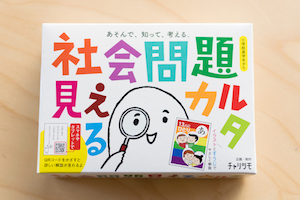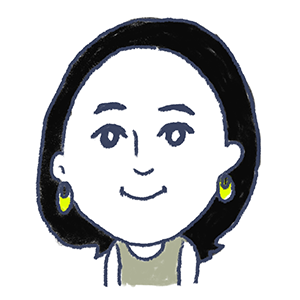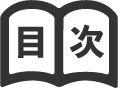シャティーラ難民キャンプのサッカークラブの話(スポーツのチカラ vol.1)

連載スポーツのチカラ
開催か中止か、有観客か無観客か、最後まで揉めにもめた東京五輪が、ついに無観客開催というカタチでスタートしました。
世界的なパンデミックで、社会が混乱する中、開催に躍起だった日本政府や大会関係者は“スポーツのチカラ”という言葉を何度も繰り返し発信し、五輪の意義を訴え続けてきました。
しかし、何度も耳にするうちに、「そもそも“スポーツのチカラ”って、なに?」なんて疑問を抱いた人は少なくないのではないでしょうか。
この言葉が多用され、その効力が徐々に薄れ始めた頃、私たちが出会ったのが、レバノンのシャティーラ難民キャンプにあるサッカークラブ“パレスチナ・ユース・クラブ”を支えるメンバーのみなさんです。
中東・レバノンで暮らす難民の子どもたちに、サッカーできる環境を届ける。そんな活動を続ける彼らの語りの中で見えてきたものこそ、まぎれもないスポーツのチカラでした。

シャティーラ難民キャンプのサッカークラブを支える大人たち
-
 法貴潤子さん普段日本にいる林さんと、シャティーラ難民キャンプをつなぐパイプ役。レバノン在住の日本人を含めた外国人を交流試合に連れて行くコーディネート業務も担当。
法貴潤子さん普段日本にいる林さんと、シャティーラ難民キャンプをつなぐパイプ役。レバノン在住の日本人を含めた外国人を交流試合に連れて行くコーディネート業務も担当。 -
 林一章さん日本でサッカーコーチやサッカー選手としてプレーしながらチャリティイベントを開催し資金を集めている。2019年にはシャティーラ難民キャンプを訪れ、子どもたちと交流。
林一章さん日本でサッカーコーチやサッカー選手としてプレーしながらチャリティイベントを開催し資金を集めている。2019年にはシャティーラ難民キャンプを訪れ、子どもたちと交流。  マジディさんシャティーラ難民キャンプ・サッカー教室のコーチ。自身もパレスチナ難民。
マジディさんシャティーラ難民キャンプ・サッカー教室のコーチ。自身もパレスチナ難民。
ここから連載初回
スタート!
スポーツのチカラ vol.1知っていますか?レバノンという国を。そこに暮らす難民のことを。
“スポーツのチカラ”について考える本連載。舞台は、レバノンです。
「レバノン」と聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか?
カルロス・ゴーン?
中東にある国?
︙
多くの人がもつイメージはそのくらいかもしれません。
ひょっとしたら、中東にあることすら、あいまいな人も結構いるのではないでしょうか?
じつはこのレバノンという国、中東と聞いて皆がイメージするであろう砂漠もラクダもないのだそう。そして元々はキリスト教徒の多かった地域をベースに作られた国なのだとか。
そんな未知の国、レバノンに住んで10年の
連載の一回目の今回は、レバノンがどんな国なのか、難民キャンプがどういったところなのかについて、法貴さんにお伺いします。
プロフィール
-

-
法貴 潤子 Simsim Kitchen主催、翻訳・コーディネーター。
南イリノイ大学(米国)人類学部BA。ジャワハルラール・ネール大学(インド)国際政治学部MA、ロンドン大学東洋アフリカ学院(イギリス)開発環境政策学部M.Sc.
旅行した国70か国、住んだ国8か国。インド在住5年、レバノン在住10年目。ベイルート・セント・ジョゼフ大学で3年半教えた後、NGO勤務などを経て、フリーに。
レバノンにいる難民への支援活動をしながら、難民女性を講師とした料理教室プロジェクトを開催したり、林一章さんが手掛けるサッカー教室で現地コーディネーターとして活動している。
取材メンバー
-
 けいしん
けいしん
-
 ふなかわ
ふなかわ
-
 ばんゆかこ
ばんゆかこ
ラクダも砂漠もない!?中東の国「レバノン」ってどんなトコロ?
今回は「スポーツのチカラ」をテーマにしたインタビュー連載の第一回。この連載では、レバノンにある「シャティーラ難民キャンプ」にあるサッカークラブの活動を掘り下げていきます。
このクラブはおもにパレスチナ難民、シリア難民の子どもたちが参加するサッカークラブ。元プロサッカー選手・林一章さんが、日本で開催するチャリティイベントなど資金を集め、クラブの活動支援に充てています。
初回となる今回は、クラブの現地コーディネーターを務める法貴さんに、「レバノン」という国についてイロイロお聞きしたいと思っています。
法貴さんはレバノン在住歴10年と聞いていますが、サッカークラブのサポート活動を始めたきっかけはなんだったのでしょう?
実は、もともとわたしは全然やるつもりがなかったんです(笑)
コトの発端は、難民キャンプに数日宿泊していた日本人の学生さんでした。
キャンプに宿泊していた彼は、「キャンプのために何かしたい!」と思ったらしく、私に相談してくれたんです。彼自身サッカーが好きだったので、「日本とキャンプをつなげてサッカーのプロジェクトがしたいです」と言われて、共通の友達にカズさん(林一章さん)を紹介してもらいました。
ところがその学生さんはいろいろ忙しくなったようで、いつの間にか抜けてしまいました。しかし、カズさんも実際にレバノンに来てプロジェクトがスタートしてしまったので、やめるにやめられず…しかたなく私がコーディネーター役を引き受けた、というのが正直なところです。
でもまあ、カズさんもとても楽しんでプロジェクトをやっているし、キャンプの子どもたちもとても喜んでくれているので、結果オーライといったかんじですね(笑)
結構ゆるい感じで始まったんですね(笑)
でもありますよね。言い出した人がいなくなっちゃうパターン。
「レバノン」って、日本に住む人にはあまりなじみがないかと思いますが、いったいどんな国なんでしょう?
レバノンは中東の国の1つで、シリアの一部を切り取ったような形をしています。西側は地中海、北〜南東がシリア、南がイスラエルに接しています。
もともとこのあたり※は「大シリア」と呼ばれるエリアの一部で、その中でキリスト教徒がたくさん住んでいた場所を切り取ってレバノンにしたんです。
独立前はフランスの植民地だったので、その影響を強く受けています。町並みもどことなくパリに似ていることから、かつては「中東のパリ」なんて言われていました。
政府の公式書類や看板も、フランス語とアラビア語の両方で書かれていることが多いです。

面積は岐阜県くらい。人口は500〜600万人と言われているんですけど、レバノン人って他の国に働きにいく人たちがたくさんいるので、実際には600万人も住んでいないと思います。
なぜ「思います」といったかというと、実はレバノンでは国勢調査を1932年を最後に、その後行われていません。なので、現在の正確な人口は誰にもわからないんです。レバノンが独立したのは1943年ですから、独立してから一度も統計を取っていないことになりますね。
100年近くも統計をとってないなんて驚きです。どうして統計をとらないのでしょう?
レバノンの社会システムのほとんどが各宗教の宗派に基づいて行われているためだと思います。
例えば、国会の議席数は宗派ごとに数が決まっていますし、公務員の数も宗派間のバランスを取ることが求められます。統計をとって各宗派の人口がきちんと分かってしまうと、国会の議席数も変わっちゃう。力を持つ既得権益層はそれが嫌だから、「あえて統計は取らずに黙っておこう」って感じです。
どの宗派の人たちに有利な制度になんですか?
昔はキリスト教徒の人口が過半数を超えていたため、国会の議席数もキリスト教の宗派が多く割り振られていました。1932年の国勢調査をもとに、キリスト教とイスラム教が6:5の割合でキリスト教が多数になるよう議席配分されていたんです。
その後、1989年にターイフ合意というのが結ばれて、キリスト教・イスラム教で半々の議席数になりました。でも実際は、現在の人口の三分の二ほどがムスリムではないかと言われています。
おもな宗派と国会の議席数
レバノンの国会(国民議会)は一院制で、議員の任期は4年。総議席数は128。
| 宗派 | 議席定員 | |
|---|---|---|
| キリスト教 (64議席) |
マロン派 | 34 |
| ギリシャ正教会 | 14 | |
| ギリシャ・カトリック教会 | 8 | |
| アルメニア教会 | 5 | |
| アルメニア・カトリック教会 | 1 | |
| プロテスタント | 1 | |
| その他宗派 | 1 | |
| イスラム教 (64議席) |
スンナ派 | 27 |
| シーア派 | 27 | |
| ドゥルーズ派 | 8 | |
| アラウィー派 | 2 | |
| イスマーイール派 | 0 |
レバノンにはどれくらいの宗派があるんですか。
レバノンでは正式に18の宗教が認められています。うち12はキリスト教の宗派です。
イスラム教徒やドルーズ教徒もいますが、キリスト教の影響も強いため、中東の中では文化的自由度が高い国です。お酒も飲めるし、服装も自由です。言論の自由も結構ありますよ。
僕たちが思い描く「中東」とはイメージが違いますね。
気候も特徴的です。「中東」って言うと砂漠のイメージがあると思うんですけど、レバノンには砂漠はないし、ラクダもいません。冬にはけっこう雪が降りますし、スキー場もあるんですよ。だから「中東のスイス」と呼ばれていた時期もあります。
私が住んでるのは地中海の海沿いの街なので暖かいんですけど、ちょっと山のほうに登っていくと今(取材時2021年2月)でも雪が積もっているので、違う国に来たようにも感じます。


イスラム教、砂漠、ラクダ…といった中東のイメージが覆されますね。
レバノンでは18の宗教が存在していながらも、どうやって国の政治をうまく進めているのか気になりました。
簡単に言うと…うまくやってません。問題だらけ(笑)
国が崩壊せずに何とか持ちこたえている、という意味ではうまくやっているかもしれませんが、宗派間の争いとかはもう、しょっちゅうあります。
“争い”と言っても、必ずしも銃の打ち合いというわけではありません。学校、就職、結婚に至るまで、生活の中に宗派による分断が深く入り込んでいる、という意味での争いです。
学校もイスラム教系とキリスト教系とかざっくり分かれています。もちろん中にはキリスト教徒の学校に行くイスラム教徒の人もいますし、無宗教を謳う学校もありますが、社会全体が宗派の影響を強く受けています。すごく小さい国なのに、コミュニティ間で軋轢があったり、仲が悪かったりするのは、昔からずーっと変わらないみたいです。
でも、こうやって問題を抱えつつも、お互いあまり干渉せずになんとか丸くやっていくというのが、たぶんレバノン流なのかな…と思います。
過去に宗教間での大きな衝突はなかったんですか?
1975年から1990年まで15年間にわたる“レバノン内戦”がありました。その時にだいぶ殺し合ったので、「もうやめとこう」っていう空気があると思います。※
今でもコミュニティ間の喧嘩が大きくなって、撃ち合いに発展することがごくたまにあります。でもそんなときも「このまま広げちゃうと内戦のときみたいに止まらなくなっちゃうからやめとこ」みたいな思いがあるからか、最終的には思いとどまる、というのの繰り返しだと思います。
内戦の記憶があるから、大きな争いに発展しないんですね。
そうですね。内戦が終わったのが1990年なので、たくさんの人が悲惨な歴史を自分ごととして覚えています。だから、自制がきく。でもいつか内戦を覚えている人が少なくなったら、また戦争になるかもしれませんよね。
自分たちの歴史を伝えていくことの重要性を感じますね。学校教育でもそうした過去の継承を重視しているのでしょうか。
そこが問題なんですが、レバノンでは内戦中のことを学校で教えないんですよ。
レバノンの歴史の教科書は第二次世界大戦で終わっています。新しい教科書を作る委員会などで話し合いが行われたことはありますが、今でも教科書で内戦のことを記述するには至っていません。これも政治的な理由が大きいです。
現在、各政党のリーダーになっている国会議員の多くは、内戦のときに殺し合った武装勢力のリーダーだった人たちです。お互いに殺し合った内戦における、自分たちの加害行為についてはあまり話してほしくない。また、各グループ間で内戦の歴史的記述に関して合意が取れない。だから、内戦に関する歴史については学校で教えていないんです。
そのため、当時を経験していない若い人たちは、内戦についてあまりよく知りません。
難民キャンプってどんなとこ?
難民はどこからくるの?
法貴さんたちは、レバノンの中の“難民キャンプ”でサッカー交流をしてるんです。「難民キャンプ」という言葉を聞いたときに、私はイメージがあまり湧かなかったんですが、どういったところなのでしょうか?
レバノンには大きく分けて2つの「難民キャンプ」があります。
ひとつ目がパレスチナ難民のキャンプ。
彼らは1948年以降に国を追われた人たちなので、70年以上前にパレスチナからやってきた人たちです。だから今は3代目、4代目、5代目くらいになっています。
レバノンには、彼らパレスチナ人が居住する政府公認のキャンプが12ヶ所あります。国連がセットアップしたものです。
キャンプができた当初、パレスチナ難民がこんなに長い間滞在するとは誰も思っていませんでした。難民キャンプもはじめは“テント”のキャンプだったんですね。
でもパレスチナ問題がいつまでも解決せず、難民の滞在が長期化した結果、今はテントではなくてコンクリートの建物が並ぶ光景に変わっています。
キャンプに入ると貧しい感じがするのはあるんですけど、それ以外は普通の町とあまり変わらないように見えるので、難民キャンプだと言われなきゃわかりません。特にベイルートにある難民キャンプはゲートとかがあるわけでもなく、フラフラと歩いていると知らずに入り込んでしまうくらい町の一部と化しています。※

もうひとつがシリア難民のキャンプです。
シリア難民が来たのは2011年以降。比較的新しいので、今はまだテントに住んでいる人もいます。
シリア難民キャンプは、正式にレバノン政府から認められていません。みんな普段は「キャンプ」と呼んではいますが、レバノン政府は「informal settlement(非公式な居住区)」という言い方をしています。レバノン政府からすると「認めてないけど、実際に誰かが住んでいる場所」っていう位置づけなんですね。
なので、国連などのレポートでもレバノンのシリア難民について書く場合はキャンプという言葉ではなく、informal settlementという言葉を使っているようです。
シリア難民の方が住んでいるキャンプの写真を見たことありますか?
見たことないです。
よく報道されるのは、屋根に雪が積もっている四角いテント。ただ、実際にこういうテントで生活しているシリア難民は全体の20%くらいで、あとの80%は普通のアパートに住んでいます。
家賃払って借りたり、まだ建てかけの建物にみんなで寄り集まって住んでいたりします。

一言で難民キャンプと言っても、違いがあるんですね。パレスチナ難民とシリア難民のキャンプはきっちり別れているんですか。
そうとも言い切れないんです。実はパレスチナ難民キャンプにシリア人難民が一緒に住んでいることも多いです。けれども、70年以上前に来たパレスチナ難民と新しく来たシリア難民の間には軋轢もあります。
難民に関与しないレバノン政府の本音「もう来ちゃったから仕方ないけど…」
レバノン政府は自国内にいる難民に対して、どのような支援をしているのでしょう?
レバノン政府は基本的に「関与しません」というスタンスです。非公認のシリア難民キャンプだけでなく 、公式に認めているはずのパレスチナ難民キャンプに関しても関与しようとせず、もちろん支援もありません。
だから、上下水道や電気などのインフラや、ゴミ収集などの行政サービスは難民キャンプにはありません。国連や住民が協力しながら自分たちでインフラ整備をしたりゴミ収集をしたりしています。電気も自分たちの発電機で発電したりして。一部ではキャンプの外の電線から勝手に引っ張ってきて問題になったりもしていますが。
70年も歴史があるのに、電気も通っていないんですね。
そうです。レバノン政府はパレスチナ難民の面倒は見ないというスタンスです。
レバノンは「難民条約」に加入していません。だから「自分たちには難民を世話する責任はない」というのがレバノン政府の言い分です。
レバノンは対人口比で見た難民受け入れ数が世界でも最も多いと聞いています。※
たくさんの難民を受け入れている寛容な国なのかと思っていましたが、「いてもいいけど特に世話しないよ」っていうのがレバノンのスタイルなんですね。
そうですね。寛容だから受けいれているわけじゃなくて、「なんかもう来ちゃったから仕方ないけど、本当は来てほしくない」、そんな感じです。
じゃあ、さっきの写真のようなテント暮らしのシリア難民に対しても、政府は何もしないんですかね?
いわゆるテントに住んでいるシリア難民の場合だと、またちょっと事情が違いますが政府が何もしないのは同じです。
彼らはベイルート(レバノンの首都)とかではなく、田舎に広がる畑などにテントを張るんです。レバノン人の地主と交渉するのはNGOや国連。「一年間いくらでここに住ませてほしい」みたいな感じで交渉することが多いようです。
文字通りの仮住まいですね。はやく安心して故郷に帰れればいいですが、問題が長期化した場合は、シリア難民もかつてのパレスチナ難民のように、テントを出て、コンクリートなどで建てた家に移行していくんでしょうか?
パレスチナ難民の前例があるから、難しいかもしれません。
レバノン人の中には、「(パレスチナ難民は)一時的にいるだけだったはずが、コンクリートの家まで建てて、ずっといるつもりじゃん」って感じで怒りを感じている人もいます。
レバノン政府としては、シリア難民の定住に繋がるコンクリートの建造物は建てさせないというのがポリシーです。だからシリア難民は畑にテントを張って暮らしている人もいるんです。シリア難民がコンクリートを敷いたり、ブロックを積んだりすると、レバノン政府から撤去命令が出されることもあります。
なかなか難しい問題ですね。レバノン人はかつてのパレスチナ難民を受け入れたことへの後悔を繰り返さぬようシリア難民を冷遇している。
レバノン人の中には「パレスチナ人もシリア人も、呼んでないのに勝手に来た」と思う人もいるでしょう。
パレスチナ難民からしたら「ちょっと避難するつもりだったのに、国に帰れなくなっちゃったから仕方ない。どうしろっていうんだ!」というのがある。
シリア難民に対しては「もうシリア帰れるじゃん、戦争※終わったんだから帰ればいいのに」とレバノン人はよく言います。
レバノンにいるシリア人は、帰れる状況にあるんですか?
たしかに、首都のダマスカスなど一部の地域には帰れるといえば、帰れるかもしれません。圧倒的優位な現政権(アサド政権)のお膝元ですし、長い戦闘も収まり治安は安定していると言われていますから。
それでも、シリア難民からすると、なかなかすぐに帰ることはできない“事情”があります。
例えば、若い男性は、もし今、兵役があるシリアに帰ってしまうと兵役に取られて、政府軍のために戦わなきゃいけません。しかし、政府軍に抑圧されて逃げてきた難民の人からしたら、政府軍は敵。「敵の軍隊の一員として、同胞と戦うことはできない」という思いがあって、故郷に帰れないでいる人たちが多いんです。
他にも内戦によって自分の村が全部壊されて、帰る場所を失った人もいます。
難民のみなさん、それぞれに事情があるんですね。
あとパレスチナ難民とシリア難民の間でも、差別があります。パレスチナ難民からすると「自分たちのほうが先に来ていた」という意識があるんですよね。
パレスチナ難民キャンプにシリア難民が逃げてきた当初は、「同じ難民だね」といった感じであたたかい歓迎ムードだったんです。
だけど、シリア難民の居住期間が長くなるにつれ※て、関係性が変わってきてしまいました。
パレスチナ難民がシリア難民に仕事を取られたり、国連やNGOによるシリア難民向け支援が広がる反面、パレスチナ難民への支援が縮小されたりという状況が起きてきたんです。
「本来は自分たちがもらえるはずだったものを、シリア難民に取られた」というパレスチナ難民の感覚が、シリア難民に対する差別の形になって表出しているのです。
長い期間のうちに次から次に様々な人々が関わり、事情が複雑化していったんですね。
知れば知るほど複雑ですよね。 さらに、最近はレバノンの首都ベイルートでも大爆発があったり※、経済危機があって、レバノン人全般がすごく貧しくなっています。でもレバノン人は難民じゃないから国連の難民支援は受けられない。
最近は「パレスチナ難民とシリア難民はいっぱい支援されているのに、なんで私たちには支援がないの?」というレバノン人の声を聞くようになりました。
はたして、これからレバノンにいる人たちがみな幸せになるためには、どうしたらいいのでしょう。
シリア人もレバノン人も、もともと同じアラブ人として共存していた
レバノンとシリアはもともと関係がよくなかったのでしょうか?
もともとは、シリアもレバノンもパレスチナも別に国に分かれていなくて、オスマン帝国のひとつの地方だったんです。陸続きということもあり、今でも国籍は違うけど親戚同士なんてことも珍しくありません。
特にシリアとレバノンの境界あたりには、シリア側の村の人と結婚しているレバノン人とかもたくさんいます。
今ある国境は、もともとは同じアラブ人が住む地域に勝手に線が引かれて、分かれちゃっただけなんです。
レバノン人とシリア人は、方言による違いはありますが、基本的に言葉も一緒です。日本で言ったら他県の人と結婚したくらいの感覚しかなくて、彼らの中には日本人が思うような”外国人”という意識はあんまりないように感じます。
シリアが戦争になる前は、シリア人もレバノン人もお互いにVISAなしで行き来できたので、「週末にちょっとダマスカス(シリアの都市)に遊びに行こう」というレバノン人もたくさんいました。
行き来するだけでなく、当時はVISAなしで働くこともできたんです。シリアでの紛争前の段階で、100万人近くのシリア人がレバノンで働いていたと言われています。シリア人のお金持ちには、レバノンでビジネスをしている人が多くて、レバノン国内のホテルや食品系の企業はシリア人経営のことが結構あるんです。
だから、必ずしもシリア人=難民というわけではない。
紛争で逃げてきたシリア人の中には、「もともとお父さんが単身赴任でレバノンにいたから家族ごとお父さんのもとへ行く」とか、「娘がレバノン人と結婚してるから親戚ごとレバノンに移住した」という人も多くいます。
「となりの県」くらいの感覚ですか。とても近い存在だったんですね。それでも、対立はあるんですか?
そうですね。対立はあります。
レバノンはチャンスや資源が少ない国です。中東は「資源がある」イメージかもしれませんが、レバノンではガスやオイルなどの資源がありません。資源がないとみんな余裕がないので、みんなで分けたくないという気持ちがあるのかもしれません。
ただ、レバノン人は「シリア人に仕事を取られる」とよく言っているわりに、自分が直接手を動かす仕事をやりたがらない人が多いんですよ。上から指図するだけで。
農業でも、土地を持っているのはレバノン人で、農作業をするのは昔からシリア人とかパレスチナ人であることが多いです。レバノン人が自分で土をいじることはあまりない。
レストランのウェイターさんなんかも、給料が安く済むという理由でシリア人が多いですよ。レバノン人を雇うと保険に入らないといけないけど、シリア人だったら保険もいらないし賃金も半分で働いてくれるから。
外国人実習生に依存する日本と似ていますね。
でも、それってすごい不思議ですよね。日本で考えたら、愛知県と岐阜県みたいな小さな違いなのに、労働に関する扱いの差はすごく大きい。もとはみないっしょに住んでいて親戚もいるという感覚で…なんだかすごい複雑ですね。
そうですね。背景には宗教も関係していると思います。
レバノンはもともとキリスト教徒を優遇する形で作られた国です。一方、パレスチナ人とシリア人の大半はイスラム教徒。特に難民の多くはイスラム教徒です。レバノン人としては「これ以上イスラム教徒が増えると力のバランスが崩れちゃうから困る」という本音があるように思います。
レバノンの医療格差と政党がもつメディア
僕は今大学で医学を勉強しているので、ぜひ聞きたいのですが、レバノンの医療はどうなっているのでしょうか。
レバノンの医療水準はけっこう高いです。実は、人口に対するお医者さんの数がものすごく多いんですよ。ヨーロッパやアメリカに留学して、医師免許を取って帰ってくるレバノン人もたくさんいます。
ただ病院ごとの医療設備の偏りについて、よく指摘されています。
お金持ちが行く私立病院はすごくきれいで豪華な設備を揃えいて、最先端医療が受けられます。しかし、ほんの一部のお金持ち以外はプライベートの医療保険に加入していませんし、政府の保険では設備が整っていない施設で不十分な医療しか受けられないのが現状です。お医者さんの数はやたら多いのに、医療サービスが行き渡っているとはとても言えません。
また、最近の経済危機で医療関係者の多くが国外へ出る道を選んでいて、これから医療現場は大変なようです
そういえば世界的にコロナが流行してからは、最初から「病院のベッドが足りなくなる」とひたすら言い続けてもうすぐ一年になります。実際足りてないと聞きますが、なんとか粘っているみたいです。
コロナに関しては、日本も似たような感じですよ。
レバノンって、何でも“コネ”が大事な国で、医療も結局コネなんです。お金かコネ。
病院のベッドも「空いてない空いてない」と言いつつ、コネがあるとわかった途端「あ、やっぱり空いてます」みたいな話も聞きます。
日本でも新型コロナで医療崩壊のなか、無症状なのにコネで優先的に入院した政治家がいました。
今回のコロナの話でいうと、レバノンは「みんなに平等で接種します」という約束で、国際機関からワクチンの無料提供を受けたんです。「ワクチン接種に関しては、絶対コネはなしでクリーンにいきます」と報道されていました。※
ところがつい昨日、75歳以上の政治家がどこかに集められてワクチンを打ってもらったなんてニュースが流れていて、約束が違うということで政府が大批判されています。
なぜそんなにコネが大事な社会になってしまうのでしょう。
国のシステムがちゃんとしていないからですかね。国が人々の基本的な生活の面倒をみてくれない場合、いざという時は自分のコネを使ってなんとかするしかないからでしょう。
まさに“自助”の世界ですね。
ただ、ここまでの話で“メディア”は政府批判をしたり、ある程度まともに機能しているように思えます。そのギャップがおもしろいなと思ったんですけど、レバノンのメディアの状況を教えてください。
多くの国で国営メディアと民放があると思うんですが、レバノンにも国営放送があります。でもほとんどの人はそれを見ていません(笑)
みんな代わり見ているのが、各政党が持っている放送局です。大きい政党はみんなテレビ局をもっていて、彼らが自分たちの好きなことを主張する。もちろん政党によって主張が違うから、同じトピックを報道していてもこっちのメディアとあっちのメディアで言ってることが違うというのがレバノンのメディアの状況です。
でもみんなそれを分かっているから、こっちはこういうポリシーだからこう言ってるんだと割り切って見ている。だから、いくつかチャンネルを回せば何が起きたかという状況だけでなく、それに対する各政党の反応も把握できるんです。
なるほど。各局で主張が違うことがもとから分かってて、いろんな視点から情報を収集する…って、みんなメディア・リテラシー高いなぁ。
そういう事情もあって、メディアが統制されている独裁国家や、忖度文化の日本と比べると、みんないろんなことを知っていると思いますよ。
料理が人をつなぐ。法貴さんが手がける、もうひとつの活動について
法貴さんはサッカークラブ以外にも、難民キャンプで支援活動をしていると聞きました。どんな活動をしているんですか?
いろいろやっているんですが、最近チカラを入れていたのは「お料理教室」です。
料理教室で難民支援?
難民のお母さんたちによる料理教室を開催しているんです。その名も「Sim Sim Kitchen」という名前のクラスです。
私はこれまで難民のみなさんと一緒にいろいろ活動してきましたが、その関わりを通して、「支援」ではなく「仕事を作ること」が重要だと常々思ってきました
お金やものをあげる支援はシンプルです。でもそれだけだと、そのループから抜け出せなくなる恐れもあるんです。難民の人たちが、外国人を見るたびに「次は何くれるの?」みたいなメンタリティになってしまうのがすごく嫌だったんですが、キャンプの人たちと話をするなかで、その背景には「本当は働きたいけど、仕事がない」ということがわかりました。そこで私は彼らの仕事をつくる手助けがしたいと思ったんです。
ただ、仕事を作ると言っても、いきなりキャンプにいる大人全員をターゲットにすることはできません。とりあえずまずは“未亡人”の人から始めようと思いました。
アラブ社会って女性が働くのが難しいんです。今まで働いた経験ないのに、戦争で旦那さんが亡くなったり、行方不明になってしまうと、生活が本当に大変です。
「働いたことはないけれど、なにかできることがあるならやってみたい」という未亡人の彼女たちにできることはなんだろう、と考えてたどり着いたのが外国人に”アラブ料理”を教えるクラスでした。
ただ、始めてみたはいいものの、コロナの打撃をモロに受け…現在は中止しています。

郷土料理を本場のお母さんたちに教えてもらえるって、すごくいいですね。
旅をしていても、郷土料理や家庭料理に触れるチャンスはなかなかありませんよね。コロナさえなければ、もうちょっと流行っていたんじゃないかと思っています(笑)
さいごに
今日の感想
インタビューを終えて
今日の社会的な問題は、たくさんの要素が複雑に絡み合ってはじめて、私たちの眼に現れてくることを実感しました。日常生活において、人間は一対一でものごとの原因と結果を結びつけがちですが、はたして本当にそうなのでしょうか。そんな疑問が浮かび上がってきました。
また、「難民」という言葉を聞いたことがあることと、「難民」を知っていること。この二つはまったく違う状態を指しており、私はめっきり前者だということを、今回のインタビューを通じて確信しました。ものごとの意味を簡単に理解した気にならないこと。これは社会問題のみならず、日常生活で遭遇するささいな問題を考えるうえでも、非常に大切な姿勢と言えるのではないでしょうか。
(by チャリツモ けいしん)
ご支援ください
元プロサッカー選手・林一章さんは、日本でチャリティフットサルなどを開催し、世界の困難を抱える地域に住む子どもたちに、サッカーをする環境を届けるための資金集めをしてきました。しかし、新型コロナによって、1年以上活動休止を余儀なくされています。
子どもたちが思いっきりサッカーを楽しめる環境を守るため、みなさまからのご支援をお待ちしています。
ショッピングで応援する
そんななか、新たにスタートしたのが“Bola de Amizade”というブランド。Tシャツやトートバックなどを販売していて、その収益の一部は、子どもたちがサッカーをするために使われます。
オンラインショップへ寄付で応援する
お振込での寄付も募集しています。
寄付先の口座はこちらです。
| 金融機関 | 百五銀行 |
|---|---|
| 支店 | 高茶屋支店 |
| 口座 | 普通預金 746669 |
| 名義 | 一般社団法人 津市スポーツアカデミーMaravilha |