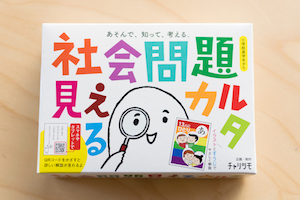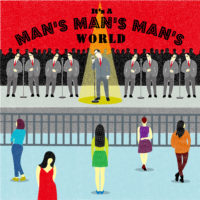めぐみのひとつぶ vol.3「食生活のモットーは“Less is More”」

こんにちは。関根愛(めぐみ)です。
梅雨入りを間近に控え、曇天や小雨もちらほら。最近は耳を澄ますと鳥の声がここ東京でもよく聴こえてきます。
アトピーをきっかけにはじめた自然食。そこには、私なりにふたつのモットーがあります。
ひとつめは『ひとは食べたもので出来ている』。
連載初回に詳しく書きましたが、私はアトピーを通し食べものと心身との深い繋がりを経験しました。それを経た今、自分の心と体がいちばん健やかでいられる食事を大切にしています。
基本とするのは、お米とお味噌汁が二大柱の和食。そこへ青菜、根菜、豆、海藻、乾物、こんにゃく、梅干し、ごまなどのマクロビオティックな食材たちをバランスよく摂り入れたものです。
調味料は至ってシンプル。醤油、自然塩、味噌、酢、植物性の出汁があれば大丈夫。世の中にあふれている食のバリエーションからすると、なんて地味かしらと思うかもしれません。
だけど『Less is More』。これがふたつめのモットー。
とても感覚的な訳ですが、「ないほうが、ある」。意訳すれば「足るを知る」とも言えるでしょうか。
成長には、次から次へとなにかが必要になるものだ、と思われる方もいるかもしれません。私は、逆の発想をしてみたいと思っています。
つまり「あれがあったほうがいいだろう、これもあったほうがいいよな」を一度やめてみる。そして「あれもなくていいかも、これもなくていいかも」という心意気を育ててみます。
それこそが心身ともに健やかに自分自身をアップデートしていくための、最も自然な方法ではないかなと感じています。
食事に限らずですが、目移りという言葉があるように、私は目で見て選ぶとついついあれもこれも要ると思ってしまいがち。
そんなときこそいったん立ち止まって、自分にとって本当に必要なものを考えてみます。
「ないほうが、ある世界」はいつも簡潔で、奥が深く、おどろくほど鮮やかです。
たとえ少ない調味料でも、有機的な育ちかたをした野菜を使って調理すれば、心も体もあっというまに満ちていくのがわかります。
今回は、そんな世界に出会うまでの私の冒険をお話したいと思います。

アトピー回復期の試練「あれもこれもまた食べたい」
見ぬふりを続けてきたアトピー。副作用を起こすこともあるつよい薬にこれ以上頼りたくない。完治したい。そう一念発起して開始した、自然食。
初めのうちは、厳格な玄米菜食をしていました。
玄米とお味噌汁をメインに茹でる、煮るなどごく軽い調理をした野菜を食べるのみ。
毎日のように食べていた動物性食品はもちろん、添加物や砂糖の入った製品、油、果物も食べない生活。大好きだったコーヒーやスパイス系のメニューも一掃です。
食べたいものを食べたいときに食べていたそれまでの食生活とはまるで比べものにならない地味な食事。
ですが、アトピーによって体だけでなく心もすっかり疲弊していた私は「一刻も早く良くなりたい」という一心で続けました。
やがて本当にふしぎなことに、一番気にしていた顔のひどい炎症が嘘のように消え、全身の痒みや痛みも引いていきました。
ところが順調に回復してきた矢先に、また新たな試練が待っていました。
「あれがまた食べたい。これもまた食べたい。」
あれほど痛い思いをしたのにも関わらず、むくむくと新芽のように湧きあがってくる制御できない欲。
「あれだったら、食べたっていいだろう。これくらいなら許されるだろう。」
今まで質素な和食ばかりで、もう飽きた。大好きなタイ料理も中華も、香辛料たっぷりのインドカレーも韓国料理も、思いっきり食べたい。ここまでがんばってある程度良くなったのだから、少しくらいいいじゃないか。
この「少しくらい」が落とし穴でした。
魚、卵、砂糖、果物などに再び手が伸びるようになりました。
とまらない「少しくらい」の誘惑
なんだ、ちょっとなら食べても何ともないじゃないか。一度火のついた「少しくらい」の加速はとまりません。
週一くらいならアイスクリームを食べてもなんともないだろう。たまにならば、肉の入ったおかずを食べたってかまわないだろう。大丈夫、だって少しだから。
その頃といえば、副作用のあるステロイド剤の服用は手離せていたものの、抗アレルギー剤は依然飲み続けていました。そのせいもあって「まあ大丈夫だろう」と強気になってしまいました。
でも実は、ちょっと汗をかくと体中痒くてたまらなくなったり、突然皮膚の一部がガサガサに荒れたり、とても回復したとは言えない状態。
「そろそろまずいよな」と焦りを感じるたび、罪悪感からいったん玄米菜食に戻るものの、ちょっと良くなるとすぐ「少しくらいいっか」。
卵をおそるおそる食べたり、肉をひとかじりしてみたり。
そんな一進一退を繰り返す生活でした。意志の弱い自分にうんざりしながら、いつも頭をよぎっていたことは「一番つらかった時の私が、今の私を見たら何て言うだろう。」
答えは決まっています。「結局、何も学んでいないんだね」。
一体どうすれば、この自己嫌悪の日々にストップをかけられるんだろう。どうしたら玄米菜食に満足できるんだろう。健康を守りながら自分らしく楽しめる食生活は、どこかにあるんだろうか。
悩みに悩み、ふさぎ込む毎日でした。
十年ぶりの海外レストランでの、店員さんのひと言「Enjoy!」
そんな時、台湾と欧州へそれぞれ3週間ずつの旅にでました。
現地ならではの食を堪能するという旅の醍醐味はあきらめて、毎日お米を炊き、お味噌汁を作ろう。お米や味噌、醤油などの調味料は日本から持っていこう。
旅先で体調を崩して満喫できなくては元も子もないので、そう気を張って出かけた私でした。
ところが実際に行ってみると、台湾にもベルリンにもパリにもヴィーガン(菜食)のレストランが沢山ありました。
台湾では菜食のことを「素食」といって、一食200円もしないで食べられるようなビュッフェスタイルの素食店が至るところに。ベルリンやパリではひと駅ごとにあるんじゃないか?というくらい、ヴィーガンのスーパーや飲食店は人びとの生活に根付いているよう。
普段と変わらない自炊をメインにしながらも、余裕のあるときにはそれらのお店に足を運んでみました。
日本とは違う野菜の扱い方や調理方法。シンプルでいて創意工夫に満ちた斬新な盛り付け方。ひとくちにヴィーガンといっても、世界ではこんなにバリエーションがあることを知りました。
ヴィーガン店で働いていた人たちが生き生きして見えたこともまた新鮮でした。
足どりは軽く、顔色には皆つやがある。好きなものの話を得意げに話すように、メニューの説明を喜んでしてくれる。
ウエイターとキッチンの人はつねに和気あいあいと話していて、鼻歌も歌ったりなんかして。仕事に対して誇りを持ちつつ心から満喫しているように見えて、東京ではあまり見かけない光景。
中でも印象的だったのが、料理をサーブしてくれる時。台湾なら嘘のない笑顔、ベルリンやパリでは“Enjoy!”のひと言が添えられる。特にこの“Enjoy!”を聴くたびに私の心の中の何か固いものが、すーっとほぐれていく感じがしました。
ヴィーガンという選択も、けっきょくは心持ち次第なんだよなあ。
ないものねだりをやめて、じぶんを大切にすることが出来たら、食生活を楽しめるようになるんじゃないかな。
ささくれた日々を送っていた私の中へ、この「楽しんで!」はさわやかな風が吹き込むように入ってきて、旅のあいだ中ずっとエコーしていました。
久しぶりに日常を遠く離れた6週間の旅は、私たちの日々を作っている食について多くのことを考えさせてくれました。
そして帰国後、感じたことや考えたことをシェアしたいと思い、ふだんの料理写真と共にinstagramに投稿することにしました。
「こんなの見て面白い人なんているのかな」と、それまで抵抗のあったSNSへの料理写真の投稿。だけど何かを恐がるよりも、じぶんの喜びをシェアしていくことにフォーカスするようにしたのです。

楽しむことができれば、重心がどんどんお腹におちていく
記録を兼ねてほぼ毎日のように料理写真の投稿を始めると、ある変化が起こりました。
それは「食生活をマネージしていくのが楽しい」というものでした。
私はこれまで食生活に対して「コントロールしなくちゃ」という意識を持っていたことに気がついたのです。なんだか圧を感じてしまう「コントロール」という言葉が苦手なのに、あえてその言葉を無意識でチョイスし、自分に課していたのです。
その気づきがあってから、言葉の重みを実感。楽しんで何かをやっていきたいのならば、自分自身が前向きになれる言葉を選んで意識してみよう。
そしてふと「マネージする」という言葉が浮かびました。「マネージ」からは、良い方向へ持っていこうとする前向きな力を感じました。そして何より「楽しく」マネージするということが想像できたのです。
このようにしてインスタグラムへの投稿を通し、食生活を「コントロールせねば」から「たのしみながらマネージしよう」という姿勢へと転換することができたおかげで、日々の食事が少しづつ楽しくなっていきました。
地味だと思っていた食事の内容も、「地味なものには滋味がある」とまで前向きに捉えられるようになったのです。
楽しめるようになると、どんどん重心が下へおりていくような感覚がありました。それまで頭や視覚を中心に考えたり捉えたりしてきたのが、お腹の辺りで感じる温かさへ自然と身を任せるようになっていきました。
そんな毎日を過ごすうち「あれも食べたいのに、これも食べたいのに」というないものねだりや焦り、「あれも食べられない、これも食べられない」という悲観が、いつの間にか消えていました。そして、お腹の辺りで必要だなと感じる食材を必要な分だけ、欲するようになりました。
今日のお店にはどんな食材が並んでいるだろうか。だれがどんな思いで育てたんだろうか。
選んだ食材をどう調理してみようか。どんな器に盛ってみようか。どうなふうに味わって食べようか。
どんなふうに写真を撮り、どんなメッセージを添えて投稿したら「地味ではなく滋味」が伝わるだろうか。また、同じような悩みを持つ人へと届くだろうか。
そんなことを考えることが、楽しい。自分の食生活をマネージし、それをシェアすることが、こんなにもわくわくするなんて。
「食べる」ということは「ものを食べる」だけの行為ではなかったのです。食べることを通して、身の回りにある豊かな循環やさまざまな繋がりに気づき、そのサイクルの中へ飛び込み思いきり楽しめばいい。そう、ついに腑に落ちたのでした。
あれもこれも食べたいと欲に埋もれていた毎日は心が乾き切っていましたが、今は自然の恵みのおかげで毎日潤っています。
Less is Moreな私の食卓
最後に、今日は私が日頃食べている『Less is More』なものをご紹介します。
どんな食べものでじぶんの体が喜ぶかは、きっとひとそれぞれ。心身一体で自分自身と対話しながら、唯一無二の食生活を発見していけたら良いですよね。何かのご参考になることがあればとても嬉しいです。

ひたすらせっせと。お米とお味噌汁で土台づくりを
お米とお味噌汁がベースの、私の食生活。
まず、お米。今は玄米をおいしいと感じるので、玄米を食べています。たまに小豆、もちきび、黒米をまぜたりして、豆や雑穀とのコラボレーションも楽しんでいます。
学生時代、炭水化物ダイエットと称し長らくお米を食べなかった時期もある私。ふり返るといつも注意散漫で軸がなく、どこかふらふら~としていました。
手間をかけて土鍋で炊いた玄米はおいしいだけでなく、食事の真ん中に据えてあげることで、心にも芯が生まれてきました。
そしてお米ときたら、お味噌汁。玄米味噌と八丁味噌(豆味噌)、麦味噌などを季節や体調によって使い分けています。
玄米味噌は、香ばしくてほっとする味。八丁味噌は、わずかな酸味とコクがあって懐かしい感じ。甘めのお味噌汁にしたいときは、白味噌をちょこっとまぜたりします。お味噌だけでぐっと風味が変わるのは感動です。
出汁はやさしい植物性の出汁で、主に椎茸と昆布です。定番の具は〈大根、長ネギもしくは玉ねぎ、海藻〉。アトピーにも良いとされる、体のおそうじを担ってくれる食材たちです。
ほんものの調味料を使えば、どんな料理もやさしくおいしい
調味料は極力シンプル。醤油、自然海塩とヒマラヤ黒岩塩、お酢、味噌だけでほぼ済んでしまいます。みりんはたまにだけ。
できるだけ余計なものの入っていない、本醸造の天然調味料の味は格別です。年月をかけて丁寧に作られた調味料には「時間の魔法」がかかっているのをいつも感じています。
少しの量をじっくり加えてあげるだけで、素材とのすなおな反応が起き、お腹の底からじんわり喜びが広がっていくような、なんともいえない滋味深い味わいになります。
時間をかけて作られた素材を使い、これまた時間をかけて作る料理には、それらが体に入ってからもまた時間をかけて体を支えてくれる力があると感じます。そのエネルギーをダイレクトに受けるからこそ、体も心も満足できる。
パパッとできてしまう量産型のインスタント食品では、今日明日の命を繋ぐことはできるのかもしれませんが、命を永らえさせる力があるとは思えません。

毎日を支える、滋養食材
常に摂ることを意識している食材は青菜、根菜、豆、海藻、乾物、こんにゃく、ごま、梅干し、そして旬のもの。
青菜はおひたしやごま和え、根菜は皮ごと煮物にしたり、きんぴらにしたり。
栄養バランスの優れた豆はごはんに混ぜたり、デザートにしたり。ほかにも和え物やサラダ、チヂミやハンバーグなど何にでも使えます。
海藻はお味噌汁に入れると手軽ですが、もずくやめかぶは、醤油とお好みのお酢でシンプルなポン酢を作ってかければ、りっぱな副菜に。
地味な食材と思われがちなのがもったいない切干大根、高野豆腐は、乾物ツートップ。乾物は太陽のパワーが凝縮されているので生きる力がつきます。高野豆腐はお肉の代わりとしてもあらゆる肉料理レシピに代用でき、万能食材といえます。
老廃物を排出してくれるこんにゃくもおすすめ。醤油をからめてじゅわっと焼いた雷こんにゃくは、ホカホカごはんによく合います。本醸造の自然な調味料で根菜などと一緒にじっくり煮物にしたら、それだけでごちそうです。
カルシウムやミネラルたっぷりのごまは、白と黒のすりごまを愛用しています。ごま油の香りが大好きですが、油の摂取を控えている私。代わりにすりごまを何にでもかけています。風味が一気に広がりますよね。
梅干しは毎日一粒ずつ。すりつぶした梅に醤油をたらして熱々の三年番茶を注いだ梅醤番茶は、「ちょっと調子がおかしいな」という時の特効薬。飲んで寝ると、次の日にはふしぎと元通りになっています。
旬の食材には、その季節にしか味わえない新鮮なエネルギーがふんだんに詰まっています。これから来る夏には、ナス科やウリ科の野菜を上手に摂って体をクールダウンしてあげるのが良さそうです。

「なにを食べるか」だけでなく「どう作るか」。そして「どう食べるか」。
それらすべてがまあるく繋がっている食事という活動を通して、自分自身を活かして生きていく力をつけることができます。あれもこれも欲しがらず、必要なものを必要な分だけ楽しんでいただくことができれば、その先には想像以上に豊かな世界が待っているのです。
少々厳しい印象を受けるかもしれませんが、終わりに高森顕徹さんという方の言葉を引用します。
『食とは、人が良くなると書く。生きている以上、少しでも向上しなければ、食べる意味がない』
食生活とはまさに「人」が自分自身を「良」く活かす生活のことをさすのだ、と私は思えてなりません。自分らしい生をひらいていくために、『Less is More』な食生活を一緒にはじめてみませんか。
関根 愛(せきね めぐみ)
「アートがどう社会と関われるか」と「じぶんらしく生きるための食養生」が活動のテーマ。座右の銘は「山動く」。俳優歴10年、アトピーによる自然食を始めてもうすぐ3年。台東区のコレクティブRYUSEN112のメンバー。
Youtubeチャンネル:めぐみのひとつぶ -体と心を癒す自然食-
note:せきねめぐみの食養生コラム
Instagram:megumi___sekine